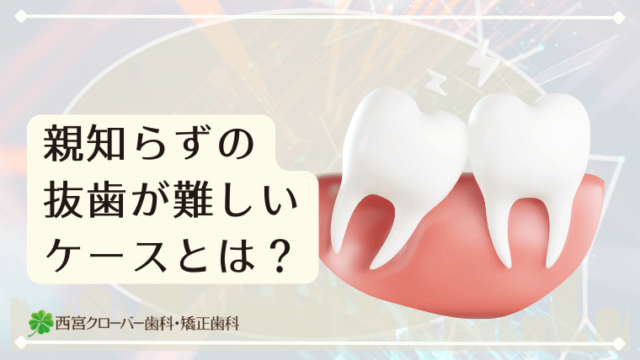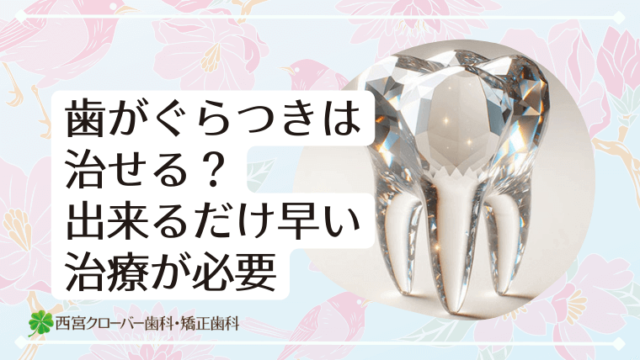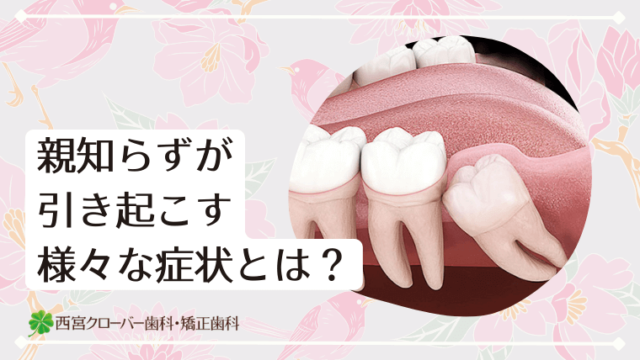口がネバネバしていると朝起きた時に不快感を覚えませんか。口の中がネバネバしている状態とはどのようなことが口腔内で起こっているか、原因や予防法、放置するとどのようなリスクが高まるかについて詳しくご紹介いたします。
口がネバネバするとはどんな状態
朝起きた時や夕方に口の中がなんだかネバネバすると感じたことは、意外と多くの方が経験されています。この口の中のネバネバは、唾液の量や質が変化していたり、乾燥や細菌の繁殖が進んでいるサインです。
- 唾液の分泌が少ないことから、粘り気のある状態になる
- 口の中に別の膜を張ったような感じになる
- 口臭や苦味を感じることもある
このような状態が頻繁に起こる場合は一時的な体調不良ではありません。口腔環境がトラブルになっていて、病気のサインである可能性があります。
口のネバネバが起きる主な原因
口のネバネバの原因について、ただ一つが原因であるということは少ないです。いくつかの要素が重なり、ネバネバの状態になると考えましょう。
唾液の分泌量の減少
口のネバネバの大きな原因になるのがドライマウスです。唾液は酸性に傾いた口腔内を中性に戻したり、自浄作用があるため口腔内を洗い流す重要な役割があります。しかし今から挙げるような要因が重なり、唾液が減少すると、唾液の性質が変わってしまいネバネバ感が出てきます。
加齢による唾液分泌量の変化
中高年になると、加齢性変化が起きます。他の内臓や皮膚、筋肉でも起こりますが、歯科領域に限ると、下記のような変化があります。
- 着色により歯が黄色くなり、もろくなる
- 歯肉が縮んでしまい、歯が長くなる
- 唇の弾力性が無くなる
- 味蕾という味を感じるところが鈍くなる
- 唾液腺が萎縮する
唾液を分泌する唾液腺が萎縮したり、唾液腺を支える筋力が低下すると、唾液量の分泌量は減少します。
ストレス・緊張状態である
唾液はさらさら成分とネバネバ成分があり、分泌を司るのは、自律神経(交感神経・副交感神経)です。リラックスしている状態だと副交感神経が優位に働くため、さらさら成分である漿液性(しょうえきせい)唾液が多く分泌されます。反対にストレスがある状態だと交感神経が優位に働き、ネバネバ成分である粘液性唾液が多く分泌されます。緊張しているときなどに口の中がネバネバとするのもこの現象が原因の一つです。
就寝中である
日中は、会話や食事など口を動かす機会が多いことから、唾液が分泌されます。ただし、就寝すると、唾液の分泌は減ってしまいます。鼻呼吸ではなく口呼吸の習慣がある人ならば、更に口腔内の乾燥は進み、ネバネバした状態になります。
水分が不足している
唾液の分泌量については、健康な大人で、一日1~1.5リットルとされています。殆どが水分ですが、わずかにカルシウムやリン酸、唾液アミラーゼが配合されます。
口腔内に細菌が繁殖
お口の中の唾液が減ると、細菌が増えやすくなります。食後にしっかりと歯磨きをしている自信がある方でも、300~700種類の1000億以上もの口腔内細菌が常在しています。歯垢(プラーク)は食べかすを元に出来る細菌の巣ですが、それを放置していると、数種類の細菌が膜のようなものを形成します。これがバイオフィルムとなり、歯以外に舌や粘膜に付着し、粘り気を強く感じるようになります。
歯周病になっている
ネバネバが慢性的に続く場合、歯周病の可能性が考えられます。歯肉と歯の間にある歯肉溝(しにくこう)に歯垢が侵入すると、歯肉溝浸出液を出して、歯垢を排出しようとします。歯茎の締まりがなく少し炎症がある場合や、膿が出ている場合は、歯周病にかかっている可能性がとても高いです。
舌苔(ぜったい)が多い
舌の表面に白っぽく付着する舌苔は、皮膚で言うと垢です。舌には凸凹があり、その部分に細菌や粘膜のはがれたものがつくと白くなります。誰しも舌苔はありますが、舌苔が多く付着しすぎると、そこは細菌の温床となり、口臭の原因になることがあります。口臭が気になっている方は除去すべきですが、歯ブラシではなく、舌ブラシで優しく取り除きましょう。
全身の病気や薬の副作用
糖尿病や腎疾患、シェーグレン症候群(唾液腺や涙腺などの外分泌腺が萎縮し、口と目が乾燥する自己免疫疾患)という膠原病の一種にかかっている場合に、お口のネバネバが症状としてあります。抗うつ剤や鎮痛剤、抗パーキンソン剤、降圧剤など多くの薬物の副作用として唾液分泌の低下もあります。また、鼻炎などの鼻疾患で口呼吸をすれば唾液は蒸発してしまい口が渇きます。治療としては、生活指導や対症療法が中心となります。
放射線治療の影響
放射線治療は、放射線を照射する部分の細胞分裂をさせないようにDNAを切断する治療です。正常の細胞は放射線の影響を受けても分裂できますが、がん細胞は放射線治療をすると成長できません。その差を利用した放射線治療ですが、口の近くに当たると、唾液腺に影響を及ぼします。唾液の減少により口腔粘膜炎になると、口の中が乾燥して痛くなったり、咀嚼や飲み込みが大変となります。
放置するとどうなる?
たかが口のネバネバと思って放置していると、意外なトラブルに発展する可能性があります。
強い口臭
ネバネバの正体の多くは細菌の塊であるバイオフィルムで、中にいる嫌気性の細菌も増殖している状態です。食べかすに含まれるたんぱく質を嫌気性菌が分解してしまうと、VSCという揮発性硫黄化合物を産生します。VSCとして挙げられるのは、硫化水素や、メチルメルカプタン、ジメチルサルファイドで、それらは口臭の原因になります。
虫歯・歯周病の悪化
自浄作用のある唾液が少ないと、食べかすや歯垢が歯や歯と歯肉の間に付着したまま残りやすいです。衛生的に保てなければ、虫歯や歯周病が進行しやすい口腔状態になります。
会話や食事のしづらさ
お口の中ネバつくことにより舌が通常通り使えず、滑舌が悪くなることがあります。咀嚼をする際には唾液が必要ですが、唾液が少なければ食べ物が口の中にまとわりつく感じがして、食事を不快に感じます。
誤嚥性肺炎のリスク
高齢者の場合、口のネバネバが誤嚥性肺炎の引き金になることがあります。20代の唾液の分泌量は、高齢者の7倍でそれが通常の量です。そのため、高齢者はドライマウスになりやすく、口腔内の細菌の量はかなり増殖しています。肺炎球菌が増殖している状態で就寝中に誤って唾が気道に入り込むだけで、肺に細菌が侵入し炎症を起こすため、口だけの問題では済まなくなるのです。
口のネバネバを解消する具体的な対処法
ネバネバを感じたときは、このような方法で一時的な改善が可能です。
こまめに水分補給をする
2000mlの水分を取ることが良いとされていますが、一度にたくさんの水分を摂取すると排泄されてしまいます。少しずつこまめに水分を飲みましょう。できれば常温の水にして、飲み物に含まれる糖分やカフェインは避けるのが良いです。
唾液腺マッサージを行う
耳下腺(耳の下)・顎下腺(顎の下)・舌下腺(舌の裏側)に唾液腺はあります。そのあたりをくるくると力を入れずにマッサージしましょう。唾液がジワッと出てきてスッキリする感覚があります。
舌ブラシで舌苔を除去
朝起きて、舌磨きを行い舌苔をこまめに除去しましょう。ただし、一日に何度も行うことや、強くこすりすぎることはよくありません。やさしく撫でる程度にしましょう。
ガムや飴で唾液を促進
キシリトールの多いノンシュガーガム、唾液分泌促進のためにキャンディーを利用するのも方法です。食事以外でもお口の中へ刺激を与えることがポイントです。
うがいで細菌を除去
アルコール含有の洗口液は、どうしてもお口の中を乾燥させてしまいます。ノンアルコールの洗口液で口内を殺菌しておきましょう。口腔内の細菌が多い起床時や、食後、就寝前がベストタイミングです。
ネバネバが数日以上続く場合は、歯科医院での診察をおすすめします。
ネバネバを防ぐ予防法と生活習慣
ネバネバの予防には、生活習慣の見直しがとても大切です。
正しい口腔ケアの習慣
食後の歯磨きを一日三回行いましょう。外出中で昼食後の歯磨きが難しい場合は、朝晩の歯磨きを念入りにしてお昼はうがいなどを行ってください。就寝前の歯磨きはデンタルフロスやタフトブラシで歯間及び歯と歯肉の境目まで丁寧に磨くよう習慣づけましょう。朝、舌ブラシで舌のケアを行うと尚良いです。
鼻呼吸を意識する
口呼吸は口を開けないと呼吸ができないため、どうしても口が乾燥します。鼻炎や鼻詰まりが見られる方は、耳鼻科で対処してもらったり、市販している口に貼るテープを試してみましょう。
食生活の改善
噛み応えのある食材を使用し、唾液分泌を促進しましょう。根菜類はしっかり噛まないといけない食材として取り入れてください。酸っぱい梅やレモンなど適量ならば良さそうですが、過剰摂取は避けておきましょう。甘いものもそうですが、過剰摂取をすると口の中が酸性に傾き、細菌が活性化して虫歯や歯周病になります。
定期的に歯科検診を受ける
定期検診を歯科で受診していると、歯石除去や歯周病及び虫歯の早期発見ができ、削るなどの対処が不要なケースがあります。定期的にクリーニングを行えば、歯や歯肉を健康に保つことができます。
まとめ

口のネバネバは、唾液の減少、細菌の繁殖、歯周病や舌苔がある、全身の不調などが複雑に絡み合って起こります。原因を理解して、適切なケアを行うことが重要で、生活習慣を見直していくとネバネバを予防することもできます。気になる場合は早めに歯科へ相談をすると、朝起きた時に口のネバネバが当たり前の生活から、すっきり快適な口内環境を取り戻すことが可能です。
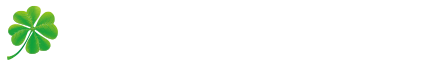
 医療法人真摯会
医療法人真摯会