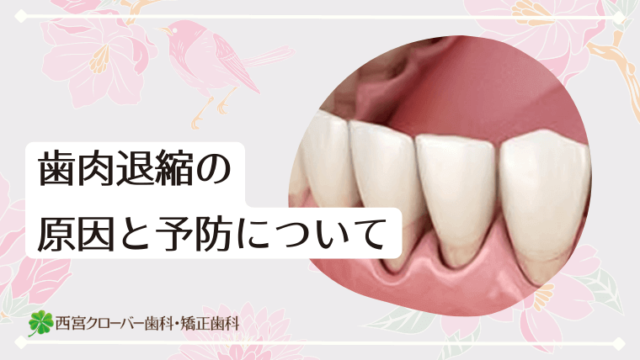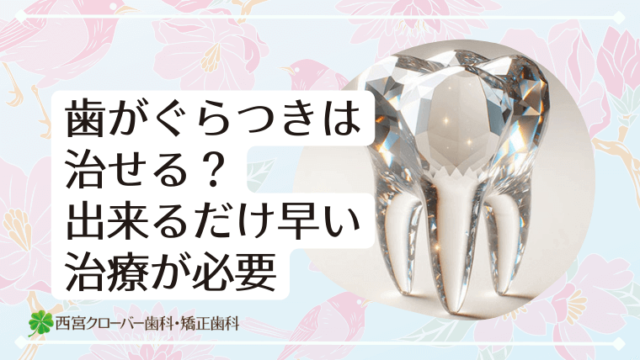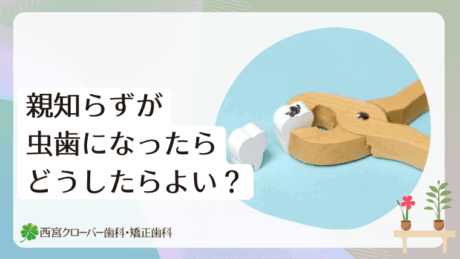
親知らずが虫歯になると、痛みや腫れなどの症状が出ることがあります。親知らずについてや、なぜ虫歯になりやすいのか、治療法や予防法についても詳しくご紹介いたします。
親知らずは生え方にクセがある歯の代表格
親知らずとは、正式には第三大臼歯や智歯(ちし)と呼ばれる、最も奥に生えてくる永久歯です。子供の頃の永久歯の生え方などは親が確認していますが、多くの人は10代後半~20代にかけて生えてくるため、親が知らないうちに生える歯と言われています。厄介な点は親知らずがまっすぐ生えないことが多いという点です。
親知らずの特徴
太古の昔、親知らずは第三大臼歯という名前の通り、咀嚼で使用していましたが、現代では顎の大きさが退化したため、親知らず自体がそもそも骨に埋まって出てこない人もいます。生えてきても現代人の顎の小ささからまっすぐに生えてくる人は少なく、横向き・斜め・半分埋まっているなど、生え方にバリエーションがあります。一番奥は歯ブラシが届きにくいことから、歯垢や食べかすが残りやすく、その食べかすが腐敗し、歯垢が歯石になって歯周ポケットに沈着すると、虫歯や歯周病などの細菌感染を引き起こします。つまり、親知らずは虫歯になりやすい条件が揃っていると言えるのです。
親知らずが虫歯になりやすい理由
親知らずが虫歯になりやすい理由として、歯の場所や、歯の形、オーラルケアのしにくさが挙げられます。
理由①:奥にあって歯磨きしにくい
正面の前歯(中切歯)を1番と呼びますが、親知らずは数えて8番目にあります。歯磨きの際に頬の内側の粘膜が当たり、歯ブラシのヘッドの角度に変化をつけづらく、まっすぐに生えていても歯と歯肉の境目などに磨き残しが起きてしまいます。斜めに生えている場合は、歯と歯茎の隙間に食べかすや汚れがたまりやすく、デンタルフロスもしっかり沿って当てることが難しいです。歯ぐきに埋もれている面積が多い親知らずは、隣接する歯に遮られ、大変磨きにくく、磨き残しが多くなってしまいます。
理由②:歯の形が複雑で汚れがたまりやすい
前歯と異なり、奥歯は歯冠に深い溝があったり、デコボコとした形状です。親知らずの形が複雑であるため、どうしても汚れや歯垢が溝に入り込みやすいです。磨き残した汚れが虫歯菌の餌になり酸を排出し、歯のエナメル質が溶けてしまいます。
理由③:半埋伏で歯ぐきが被っている
親知らずの一部のみが口腔内に露出していると、歯と歯茎の間に汚れが溜まりやすく、どうしても歯肉炎や歯周病も併発しやすいと言えます。
理由④:隣の歯が影響を受ける
親知らずの虫歯がエナメル質のみにとどまらず、象牙質や歯髄にまで広がると、隣接した手前の第二大臼歯にも虫歯が波及する可能性があります。親知らずにより機能している他の歯を失うことになってしまいます。
虫歯になったときは治療?抜歯?
では、実際に親知らずが虫歯になったとき、どのような対処を行うでしょうか。選択肢は大きく分けて次の2つです。
① 抜歯
最も一般的な対処法として、親知らずを抜いてしまうものです。特に、横向きや斜めに生えていたり、半分隠れている埋伏歯は、根本治療よりも抜歯が現実的です。抜歯をおすすめされるケースは下記の通りです。
虫歯が進行している
虫歯が進行し歯がボロボロの場合、抜歯器具が歯に引っかかりづらいですが、骨を削って親知らずを抜歯する必要があります。ただし、抜歯の難易度は高くなります。
手前の歯に悪影響を与えている
親知らずの周囲は歯磨きがしづらいため、隣接する歯や歯茎にも炎症が起きていることがよくあります。手前にある第二大臼歯は咀嚼に必要な歯ですので、その歯や歯茎に影響が及ぶと、歯の健康寿命が短くなり、また、消化器官への負担が増してしまいます。
噛み合わせに関係していない歯である
親知らずは上下左右を合わせて4本と言われますが、生えてこない患者さんもおられます。噛み合わせる機能を果たしていないため、虫歯になった場合は抜くのが賢明と言われることがあります。
今後もトラブルが予想される
レントゲン撮影を行い、今後どうしても親知らずによるトラブルが予想される場合は抜歯をおすすめされるでしょう。
歯根の肥大化
歯根の先端部分が細くなく肥大した状態を、歯根肥大と呼びます。親知らずが歯根肥大であれば、隣接する歯を押す可能性があり、歯並びに悪影響を及ぼす可能性があります。歯根が曲がっている歯根湾曲を起こしていると更に難しい症例になります。骨を削る削合という処置や、歯根分割という歯を割る処置をして、抜歯を行います。
埋伏歯に骨が被っている
歯茎の中に埋まっている歯が、骨に多く被っていると、歯に被っている骨を削り抜歯しないといけません。骨の被り具合によっては抜歯の難易度が高くなることがありますが、埋伏歯も歯並びを乱すことがあるため、抜歯が賢明です。
下顎管が近い
一般的に下顎の親知らずは、上顎の親知らずよりも抜歯しづらく難易度が上がります。下顎の親知らずの根の周囲には下顎管というものが近くあり、下歯槽神経、下歯槽動脈、下歯槽静脈が中に入っています。下顎管を傷つけると、大出血を起こしたり、神経麻痺に繋がることがあります。そのため、下顎の親知らずも虫歯であれば抜歯した方が良いですが、方法については慎重に検討し、場合によっては大学病院を紹介してそちらでの抜歯をおすすめすることもあります。
一般的にまっすぐ生えているケースは、抜歯の難易度が低く、術中の痛みやその後の腫れが少ないことが多いです。しかし、斜めや横向き、埋伏歯のケースだと痛みや腫れが強くなる傾向にあります。炎症が強い場合は、麻酔の注射が効きにくく、抜歯の際に痛みを感じやすいです。そのため、痛みを感じる場合、麻酔を追加で打つ必要がありますので、抜歯が非常に大変になります。
② 残して治療
親知らずを残して治療する場合は、他の天然歯と同様に虫歯の治療を行います。ただし、下記の二つとも満たしていることが条件です。
- まっすぐに生えている
- 他の歯としっかり噛み合っている
ブラッシングが可能で、再発のリスクが少ないと診断されれば、細菌感染した部分をしっかり削り、薬剤を詰め、詰め物や被せ物をします。奥歯で治療自体がしにくい位置であるため、無理に残すより将来的なリスクを避けて抜く方が安全なこともあります。
放置するとどうなる?
虫歯だけど、奥で目立たないし、まだ我慢できると放置してしまうのは、もっとも危険です。
放置するとこうなる!リスク一覧
- 激しい痛みや腫れを引き起こす
- 手前の大切な奥歯も虫歯になる
- 歯ぐきが腫れて智歯周囲炎を発症する
- 口が開きづらくなる
- 頬が腫れる
- 発熱する
- 蜂窩織炎(ほうかしきえん)による呼吸困難になる
最も厄介なのは、虫歯で腫れている最中はすぐに抜歯ができないことです。麻酔の効果も弱まってしまうため、まず炎症を抑えてから再度来院、という二度手間になりがちです。気になると思った段階で早めに歯科医院へ通院しましょう。
親知らずの虫歯を予防するためには
親知らずの虫歯は“なる前の予防”が一番の治療です。特にまだ痛みがない人こそ、下記の点に注意しておきましょう。
正しい歯磨きをする
親知らずの周囲までしっかり届くよう、小さめのヘッドの歯ブラシを使用しましょう。ワンタフトブラシやデンタルフロスも使用して、歯と歯肉の間も綺麗に磨いていきましょう。
口腔内をこまめにチェックする
親知らずが生えてきたと感じたら鏡で確認してください。生えてきた違和感があるけれど目視できにくい場合は、歯科医院でプロのチェックを受けましょう。
歯科でレントゲンを撮る
レントゲンを撮影すると、見えない部分に親知らずが埋まっているかどうか確認出来ます。埋伏歯の状態によって、将来の虫歯リスクや抜歯の必要性についても診断できます
気になる症状があればすぐに相談
- 以前と違って噛みにくい感じがする
- 奥の歯ぐきが腫れている
- 口臭がする
このような症状があれば、何かしらのサインということが考えられます。歯科医院を受診しましょう。
まとめ

親知らずが虫歯になるのはよく起こりがちですが、決して軽視できない問題です。親知らずは虫歯になりやすく、見えにくい歯で、治しにくい位置にあるため、治せるか抜くか診断を仰ぎましょう。放置すれば手前の歯にまで被害が及ぶため、予防のカギは、丁寧なブラッシングと定期検診です。痛くないうちにチェックしておくことが、親知らずトラブルを避ける一番の方法ですので、気になることがあれば遠慮せず、すぐに歯科医院へ相談しましょう。
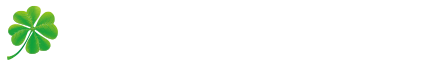
 医療法人真摯会
医療法人真摯会