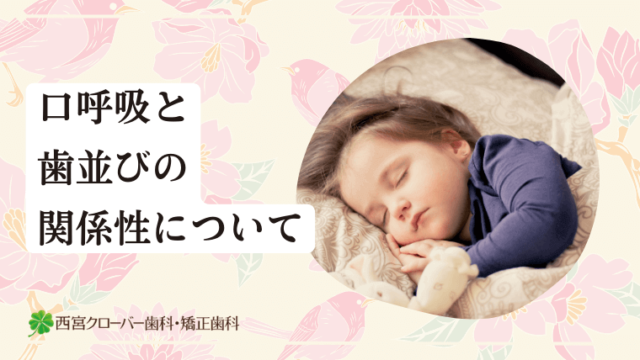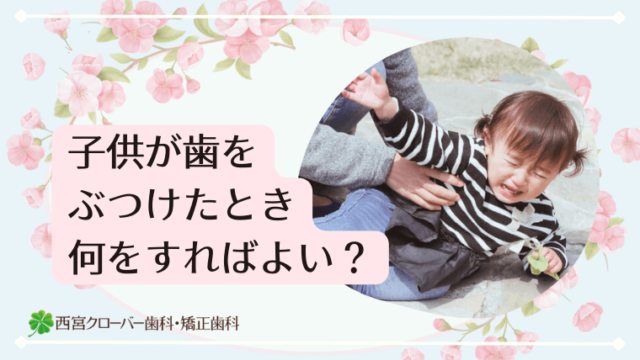「小児とは何歳まで?」「小児歯科はいつまで通える?」など、子供が大きくなるにつれ、子供がいるご家庭は疑問に思われるかもしれません。医療分野により小児の定義が異なることがありますので、詳しくご紹介いたします。
小児とは何歳まで
小児とは何歳までを指すのかというという問いは、意外と曖昧にされがちです。医療全体と歯科領域では、小児の定義に少し違いがあります。
一般医療での小児の定義
風邪などで受診する小児科を事例に挙げましょう。日本小児科学会では、小児科への通院年齢を、成人するまでというように提言しています。とはいえ、町にある一般の小児科においては、15歳(中学卒業)までを小児として診療する医療機関が多いです。理由として、15歳を過ぎると、大人と同量の薬の処方ができるという点から、大人と同じ内科通院で問題が起きないからということです。
歯科での小児の定義
小児歯科はおおよそ歯が生え始める生後6か月頃から、全ての歯が永久歯に生え変わる中学3年生(15歳)までを対象としていることが多いです。ただし、年齢で区切れないほど、顎や歯の成長状態には個人差があります。そのため、15歳を過ぎても、顎の成長がまだ終わっていない場合は小児歯科へ継続して通院するケースも考えられます。あくまで、15歳くらいが小児歯科のひとつの目安ですが、患者さんの歯の状態や精神的成熟度によっては高校生でも小児歯科で受診することがあります。
年齢別のお口の変化
子供の年齢別のお口の変化についてご紹介します。
0〜3歳:乳歯が生え始める時期
ガーゼを指に巻いて赤ちゃんのお口の中をふき取り、口の中に何かを入れても抵抗がない状態にしていきます。歯が生えてくれば、赤ちゃん用の喉を突かない歯ブラシを持たせて習慣づけます。フッ素入り歯みがき剤はごく少量から開始していきます。ただし、乳児や幼児期の指しゃぶりや口呼吸などの習癖は歯並びに影響を及ぼしますので、注意しましょう。
4〜6歳:乳歯列完成〜混合歯列期の始まり
乳歯がきちんと並んでいるかなどの歯並びをチェックします。この時期に食習慣や歯磨き習慣の見直しがとても重要です。定期的なクリーニングで歯を綺麗にし、フッ素塗布で歯を強くし、歯磨きが難しい奥歯の溝はシーラントの処置をして虫歯予防することもあります。
7〜12歳:永久歯の萌出が進む
歯磨きの技術が未熟なので、必ず子供が歯磨きをした後に、保護者が仕上げ磨きをすることを継続しましょう。混合歯列期は、生えたての永久歯と乳歯が混ざり、歯並びや噛み合わせに変化が起きやすいです。定期的に歯科医院へ通院し、なるべく早く対処できるかがカギとなります。
13〜15歳:永久歯列完成期
上顎の発達が10~12歳まで、下顎が15歳までに成長が止まります。その頃、永久歯の歯並びがほぼ完成します。自分自身での管理を習慣づける大事な時期になりますし、必要に応じて大人と同じ矯正治療を行うことも視野に入れる時期です。
小児歯科と大人の歯医者の違い
歯医者に行くならば小児歯科でも大人の歯科でもどっちでもいいんじゃない?と思うかもしれませんが、小児歯科には大人の一般歯科とは違った特徴と役割があります。
小児歯科の特徴
小児歯科と一般歯科の治療内容で差があるとすれば、虫歯予防、生えてくる永久歯の歯並びを綺麗にするということに重点をおくところです。永久歯に比べて乳歯はエナメル質がとても薄く、細菌感染をすると、虫歯はすぐに内部の象牙質や歯髄(神経)へ進行してしまいます。小児歯科は、歯の生え変わりの混合歯列期に子供が通うため、歯並びが悪くなりそうであれば、矯正への提言をもらえることがあります。歯並びが綺麗であると見た目などの審美性のみではなく、噛み合わせによる特定の歯への負担や、歯の健康を長持ちさせることができ、お口の健康を将来的にサポートできます。
- 成長発育に応じた治療と対処ができる
- 子供の心理に配慮した接し方・声かけができる
- 乳歯と永久歯の両方を理解した専門的診断ができる
- 習癖(指しゃぶり、舌癖など)もチェック対象である
対象とするお口の悩み
では、小児歯科で診療してもらえる子供のお口の悩みをご説明します。
- 虫歯
- 歯並びや噛み合わせの乱れ
- 乳歯のグラつきや早期脱落
- 永久歯の萌出異常
- 定期的なフッ素塗布や歯みがき指導
つまり、小児歯科は子どもの身体の成長に合わせたお口のトータルサポートができる専門科と言えるかもしれません。
中学生・高校生でも小児歯科へ行ける?
もう中学生(あるいは高校生)だけど小児歯科に通っていていいの?という疑問を持つ保護者さんは少なくありません。
通院しているケース
先述しましたが、 小児歯科で年齢を重ねても、特に不安がなく引き続き対処をしてくれていたり、虫歯治療や予防がメインで複雑な処置が不要な場合は、通院をしても問題がないでしょう。歯科医院から、小児歯科から一般歯科へ切り替える時期とアドバイスされるまで通院しても良いでしょう。
切り替えを検討してよいケース
矯正治療や親知らずなどで大人向けの専門治療が必要になることがあります。そのような場合、小児歯科ではなく、専門治療を受けられる医院に切り替えることをおすすめします。精神的に成熟して大人の治療環境の方が合うようになってきたころです。年齢で区切るというよりは、成長段階や治療内容で見極めることが重要です。
小児歯科を卒業するタイミングとは
そろそろ小児歯科を卒業してもいいかな?とご家庭で判断するのは悩ましいです。
卒業タイミングの目安
卒業のタイミングは下記のような基準で考えるとスムーズです。
乳歯が全て永久歯に生え変わった
全て永久歯へ生え変わるのは、平均的には12〜13歳です。顎の骨の成長によっても異なりますが、大人の口腔状態になったと言えます。
フッ素塗布などの予防処置が一段落
虫歯予防となるフッ素を歯に塗って歯質を強くするフッ素塗布は、歯のためには定期的に行わなければなりません。ただし、予防歯科のフッ素が終わってひと段落ついたならば、大人が通える歯科医院へ切り替えを検討するのも悪くないでしょう。
治療や説明の際に、本人が主体的に受け答えできるようになった
親が子供の状態を逐一説明するのではなく、本人がきちんと説明できるようになり、且つ治療の際に説明を理解して、治療を受けることができるような状態であれば、切り替えても良いかと思います。また、歯医者へ通院する状態に慣れて抵抗感がない、精神的に問題ない場合も同様です。
矯正や口腔外科などの専門治療への移行が必要になった
矯正治療や口腔外科などの専門的な治療が必要になった際、小児歯科ではなく、専門的な症例や知識のある歯科医院へ通院する方が患者さんにとって良いということも多いです。とはいえ卒業イコールさよならというよりも、小児対応から大人の対応への自然なステップアップと捉えるとよいでしょう。
まとめ

「小児とは何歳まで?」「小児歯科はいつまで通える?」かというのは、歯の成長状態と、心の成長のバランスで決まります。子どもの治療先に迷っていて通い慣れた歯医者を卒業すべきか悩んでいたり、大人の歯医者にいつ切り替えるか知りたい方は多いでしょう。小児歯科の目安は15歳くらいまでですが、 年齢のみでなく治療内容や、精神的な成熟、医院の方針も判断材料です。どのタイミングで切り替えるべきか迷ったら、今通っている歯医者さんに素直に相談してみると、成長を見守ってきたドクターは、あなたとお子さんに最適な提案をしてくれると思います。
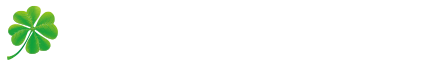

 医療法人真摯会
医療法人真摯会